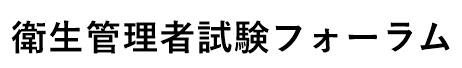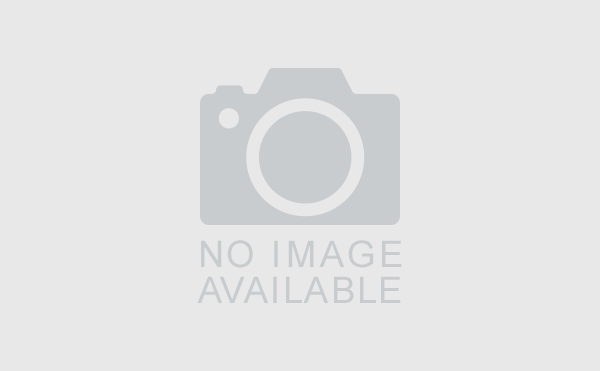第1種衛生管理者試験 2023年10月公表試験問題(過去問)の出題事項を3分でチェック!
こんにちは。衛生管理者試験 専門講師の高山です。
2023年(令和5年)10月に公表された、最新過去問(公表試験問題)の出題事項を全問整理して解説コメントを付けました。
◇問題は以下よりダウンロードできます。
第1種衛生管理者試験 2023年(令和5年)10月 公表試験問題

*****************************************************************************
2023年10月 第1種衛生管理者試験 公表試験問題(過去問)の出題ポイント解説
関係法令(有害) 10問
問1 安全衛生管理体制(衛生管理者)
=本設問の事業場の状況=
・常時400人の労働者を使用する製造業の事業場
・400人中に、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれている。
深夜業を含む業務 200人
多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
(1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
→正しい。
常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任する必要があります。
(2) 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
→誤り。
本設問の事業場は、専任の衛生管理者が少なくとも1人必要な事業場には該当しません。
■専任の衛生管理者が少なくとも1人必要な事業場
常時1,000人超の事業場
または
常時500人超の事業場で、一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
(3) 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
→正しい。
本設問の事業場は製造業で、衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができます。
また、本設問の事業場は、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者から選任しなければならない事業場には該当しません。
■衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者から選任しなければならない事業場
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は次の1~5の業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
1.多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務
2.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
3.土石、獣毛等のじんあい、粉末を著しく飛散する場所における業務
4.異常気圧下における業務
5.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
(4) 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
→正しい。
本設問の事業場は、専属の産業医が必要な事業場(常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または、常時500人以上の労働者を労働安全衛生規則第13条1項第3号に掲げる業務に従事させている事業場)には該当しません。
(5) 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。
→正しい。
特定化学物質を製造又は取り扱う作業では、特定化学物質作業主任者を選任が必要ですが、試験研究のための取り扱い作業においては選任は不要です。
問2 特別教育
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、特別教育が必要です。
問3 作業主任者
石綿作業主任者は、技能講習を修了することによって取得できる資格です。
問4 特定化学物質障害予防規則
オルト-トルイジンは、特定化学物質 第二類物質です。
問5 粉じん障害防止規則
-特定粉じん発生源に該当するもの-
・粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
・屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
問6 有機溶剤中毒予防規則
作業場所に設ける局所排気装置について、
外付け式フードの場合は、
側方吸引型・下方吸引型で0.5m/s
上方吸引型で1.0m/s
の制御風速を出し得る能力を有するものにしなければなりません。
問7 電離放射線障害防止規則
男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性が受ける実効線量の限度
緊急作業に従事する場合を除き、5年間につき100mSv、かつ、1年間につき50mSv
問8 衛生基準(立入禁止場所)
炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。
問9 作業環境測定
鉛濃度の測定 ➡ 1年以内ごとに1回
問10 労働基準法(有害業務)
超音波にさらされる業務は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しません。
労働衛生(有害) 10問
問11 空気中の有害物質
アクリロニトリル ➡ 蒸気
アセトン ➡ 蒸気
アンモニア ➡ ガス
ホルムアルデヒド ➡ ガス
硫酸ジメチル ➡ 蒸気
問12 労働衛生の3管理
A 座位での情報機器作業における作業姿勢は、椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分あて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とする。→ 作業管理
B 有機溶剤業務を行う作業場所に設置した局所排気装置のフード付近の気流の風速を測定する。→ 作業環境管理
C 鉛放射線業務を行う作業場所において、外部放射線による実効線量を算定し、管理区域を設定する。→ 作業管理
D ずい道建設工事の掘削作業において、土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備を稼働する。→ 作業環境管理
E 介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働者に対し、腰痛予防体操を実施する。 → 健康管理
問13 作業環境改善
化学物質等による疾病のリスクの低減措置について、法令に定められた措置以外の措置を検討する場合、優先度の最も高いものは、化学反応のプロセス等の運転条件の変更です。
問14 ガスによる中毒
シアン化水素 ➡ 細胞内の酸素の利用の障害による呼吸困難、けいれん
問15 騒音による健康障害
等価騒音レベルは、ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表した量である。
問16 金属による中毒
クロム ➡ 鼻中隔穿孔、肺がん、上気道がん
問17 有害光線による健康障害
レーザー光線は、おおむね180nmから1mmまでの波長域にあります。
問18 作業環境における有害要因による健康障害
低体温症は、低温下の作業で全身が冷やされ、体の中心部の温度が35℃程度以下に低下した状態をいう。
問19 局所排気装置
局所排気装置を設置する場合は、給気量が不足すると排気効果が低下するので、排気量に見合った給気経路を確保する。
問20 有機溶剤による健康障害
キシレン ➡ メチル馬尿酸
関係法令(有害以外)7問
問21 安全衛生管理体制(産業医)
常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければなりません。
問22 衛生委員会
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができます(任意) 。
作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができるという規定はありません。
問23 定期健康診断
定期健康診断を受けた労働者に対しては、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければなりません。
問24 事業場の事業場の建物・施設等に関する措置
男女別に休養室又は休養所を設けなければならないのは、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用している事業場です。
問25 ストレスチェック
ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
問26 妊産婦
妊産婦のフレックスタイム制による労働については制限は設けられていないため、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることができます。
問27 年次有給休暇
比例付与対象者の有給休暇の付与日数は、次の計算式で求めることができます。
通常の労働者の有給休暇日数×比例付与対象者所定労働日数÷5.2日
(計算後、小数点以下は切り捨てる)
本問を、計算式に当てはめると、
18×4÷5.2=13.846‥‥
小数点以下は切り捨てなので、答えは13日となります。
労働衛生(有害以外)7問
問28 健康診断
ヘモグロビンA1cは、糖化ヘモグロビンがどのくらいの割合で存在しているかを表したもので、過去1~2か月の血糖値を反映する。貧血の有無を調べるために利用されるのではない。
問29 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン
・第二種施設において、特定の時間を禁煙とする時間分煙は認められていません。
・喫煙専用室は飲食不可とされています。
問30 労働衛生管理統計
生体から得られたある指標が正規分布である場合、そのばらつきの程度は、分散や標準偏差によって表される。
問31 腰痛予防対策指針
負荷心電図検査は、腰痛健康診断の項目にはありません。
問32 脳血管障害
くも膜下出血は、脳動脈瘤が突然破れ、くも膜の収まっているところに出血し脳を圧迫する病気で、突然の激しい頭痛で発症する。脳動脈瘤が破れて数日後に発症するのではない。
問33 食中毒
感染型食中毒は、食物に付着した細菌そのものの感染によって起こる食中毒で、サルモネラ菌によるものなどがあります。
問34 BMI
BMI=体重(kg)÷身長(m)²
80÷(1.75×1.75)=26.122…となるので、最も近い値は26となります。
労働生理 10問
問35 血液
白血球のうち、リンパ球には、Bリンパ球、Tリンパ球などがあり、これらは免疫反応に関与している。
問36 心臓の働きと血液循環
心拍数は、右心房に存在する洞結節からの電気刺激によってコントロールされている。
問37 呼吸
呼吸のリズムをコントロールしているのは、脳幹の延髄にある呼吸中枢である。
問38 栄養素
炭水化物(糖質) → アミラーゼ・マルターゼ
脂質 → リパーゼ
蛋白質 → トリプシン・ペプシン
問39 肝臓
-肝臓の機能-
・コレステロールの合成
・尿素の合成
・胆汁の生成
・グリコーゲンの合成・分解
-肝臓の機能ではないもの-
・ヘモグロビンの合成 → ヘモグロビンは骨髄で作られます。
問40 代謝
エネルギー代謝率は、動的筋作業の強度を表すことができるが、精神的作業や静的筋作業には適用できません。
問41 筋肉
刺激に対して意識とは無関係に起こる定型的な反応を反射といい、四肢の皮膚に熱いものが触れたときなどに、その肢を体幹に近づけるような反射は屈曲反射と呼ばれます。
問42 感覚器・感覚
耳についての出題。
前庭は体の傾きの方向や大きさを感じ、半規管は体の回転の方向や速度を感じる。
問43 ストレス
外部からの刺激であるストレッサーは、心身の活動を活発にしたり、抑圧したりという反応のひきがねになります。抑圧するばかりではありません。
問44 ホルモン
コルチゾール = 副腎皮質 = 血糖量の増加
衛生管理者試験では、過去問の類似問題が多く出題されます。
見たことがない新しい問題も何問かは出題されますが、過去問をしっかりマスターしていれば合格できます。
過去5年分(10回分)の過去問を繰り返し学習することをおすすめします。
試験に出るポイントに的を絞った講義と、実践的な問題練習を行う講習会を、東京とZOOMで開催しています。
>>衛生管理者試験対策講習会 詳しくはこちらへ
企業内講習(ZOOMオンライン・出張講習)の講師を承ります。
>>衛生管理者試験 企業内講習会(全国) 詳しくはこちらへ