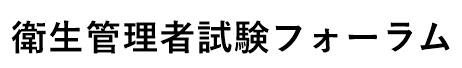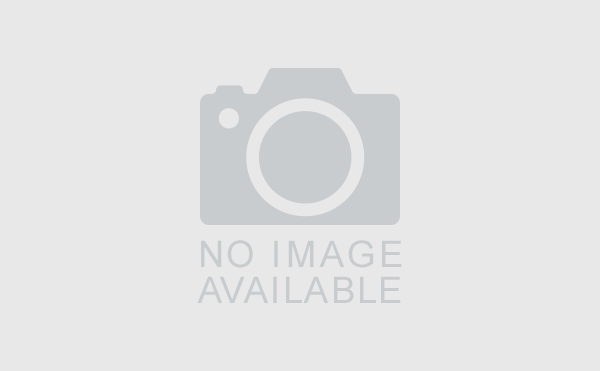こんにちは。衛生管理者試験対策講習会 専門講師の高山です。
今回のブログのテーマは【呼吸】です。
1.出題頻度は?
過去問 直近10回中【呼吸】の問題は9回出題されています。
※2017年4月~2021年10月までの過去問10回分の当社分析による。
※過去問(公表試験問題)は、衛生管理者試験の主催団体である 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 が年2回(4月・10月)HP上で公表しています。
2.呼吸の出題ポイント
・呼吸運動は、肋間筋(ろっかんきん)、横隔膜(おうかくまく)などの呼吸筋によって胸郭内容積を周期的に増減し、それに伴って肺を伸縮させることにより行われる。
・横隔膜が下がり、胸郭内容積が増し、胸腔の内圧が低くなるにつれ、鼻腔や気管などの気道を経て肺内へ流れ込む空気 → 吸気
・胸郭内容積が減り、内圧が高くなるにつれ、肺が収縮し、肺内から体外に出される空気 → 呼気
・肺胞内の空気と肺胞を取り巻く毛細血管中の血液との間で行われるガス交換を外呼吸(肺呼吸)という。
・全身の組織細胞とそれをとりまく毛細血管中の血液との間で行われるガス交換を内呼吸(細胞呼吸)という。
・呼吸に関与する筋肉は、延髄にある呼吸中枢によって支配されている。
・呼吸中枢がその興奮性を維持するためには、常に一定量以上の二酸化炭素が血液中に含まれていることが必要。
・成人の呼吸数は、通常、1分間に16~20回であるが、食事、入浴、発熱によって増加する。
2.問題練習(正誤問題)
Q1 呼吸運動は、気管と胸膜の協調運動によって、胸郭内容積を周期的に増減させて行われる。
Q2 肺胞内の空気と肺胞を取り巻く毛細血管中の血液との間で行われるガス交換は、外呼吸である。
Q3 呼吸に関与する筋肉は、間脳の視床下部にある呼吸中枢によって支配されている。
Q4 血液中の二酸化炭素濃度が増加すると、呼吸中枢が刺激され、呼吸が速く深くなる。
解答
A1 誤り。呼吸運動は気管と胸膜の協調運動で行われるのではなく、横隔膜や肋間筋などの呼吸筋の協調運動で行われます。
A2 正しい。肺胞でのガス交換は外呼吸です。
A3 誤り。呼吸に関与する筋肉は、延髄にある呼吸中枢によって支配されています。
A4 正しい。体を動かして血液中の二酸化炭素が増加すると、呼吸中枢が刺激され、呼吸が速く深くなります。
今回は、呼吸について書きました。
今後も、衛生管理者試験によく出る内容についてブログを書いていきますのでよろしくお願いします。
試験に出るポイントに的を絞った講義と実践的な問題練習を行う試験対策講習会を開催しています。
■衛生管理者試験対策講習会(東京・神奈川・千葉・埼玉)詳しくはこちらへ
貴社内での衛生管理者受験準備講習の講師を承ります。出張講習とZOOM講習がございます。
■衛生管理者試験 企業内講習会(全国)詳しくはこちらへ