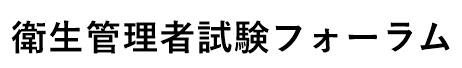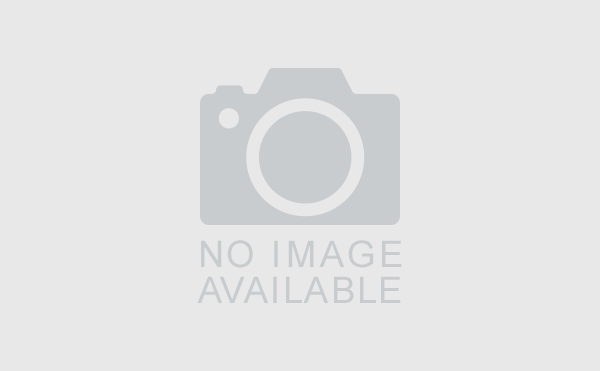第1種衛生管理者試験 2022年4月公表試験問題(過去問)の出題事項を3分でチェック!
こんにちは。衛生管理者試験 専門講師の高山です。
2022年(令和4年)4月に公表された、過去問(公表試験問題)の出題事項を全問整理して解説コメントを付けました。
◇問題は以下よりダウンロードできます。
第1種衛生管理者試験 2022年(令和4年)4月 公表試験問題

***********************************************************************************
2022年4月 第1種衛生管理者試験 公表試験問題の出題ポイント解説
関係法令(有害業務)10問
問1 安全衛生管理体制(有害業務)
多量の低温物体を取り扱う業務では、衛生工学衛生管理者の選任は不要。
問2 作業主任者
乾性油を入れてあるタンクの内部における作業 → 酸素欠乏危険作業主任者
圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室の内部において行う作業 → 高圧室内作業主任者
問3 機械等に関する規制
排気量40cm³以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡・貸与・設置してはならない機械に該当します。
問4 特定化学物質 第一類物質(製造許可物質)
インジウム化合物は、特定化学物質 第二類物質であるため、製造許可は不要。
問5 石綿障害予防規則
石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、
①作業環境測定の記録
②作業の記録
③石綿健康診断個人票
を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
問6 有機溶剤中毒予防規則
作業場所に設ける局所排気装置について、囲い式フードの場合は0.4m/s、外付け式フードの場合は、側方吸引型・下方吸引型で0.5m/s、上方吸引型で1.0m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにしなければならない。
問7 労働安全衛生規則(有害業務)
炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
問8 電離放射線障害防止規則
① 管理区域とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3か月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域又は放射性物質の表面密度が法令に定める表面汚染に関する限度の10分の1を超えるおそれのある区域をいう。
② ①の外部放射線による実効線量の算定は、1cm線量当量によって行う。
問9 有害業務に係る健康診断
有機溶剤業務 ➡ 尿中の代謝物量の検査など(有機溶剤等健康診断)
放射線業務 ➡ 皮膚の検査など(電離放射線健康診断)
鉛業務 ➡ 尿中のデルタアミノレブリン酸量の検査など(鉛健康診断)
石綿業務 ➡ 胸部のエックス線直接撮影検査など(石綿健康診断)
潜水業務 ➡ 四肢の運動機能の検査など(高気圧作業健康診断)
問10 年少者
超音波にさらされる業務は、満18歳に満たない者を就かせることができる。
労働衛生(有害業務)10問
問11 化学物質のリスクアセスメント
化学物質等による疾病のリスクの低減措置を検討する場合、優先度の高い順に次の通り。
【優先度の高い順】
1.化学反応のプロセス等の運転条件の変更
2.化学物質等に係る機械設備等の密閉化
3.作業手順の改善
4.化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用
問12 作業環境測定
A測定の第二評価値は、単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値。
問13 ガスによる健康障害
一酸化炭素中毒は、血液中のヘモグロビンと一酸化炭素が強く結合し、体内の各組織が酸素欠乏状態を起こすことにより発生する。
問14 有機溶剤による健康障害
-生物学的モニタリングの指標としての尿中代謝物-
テトラクロロエチレン ➡ トリクロロ酢酸
問15 粉じんによる健康障害
石綿(アスベスト)➡ 石灰化を伴う胸膜肥厚や胸膜中皮腫
遊離けい酸 ➡ けい肺結節
問16 作業環境における有害要因による健康障害
減圧症は、潜函作業者、潜水作業者などに発症するもので、高圧下作業からの減圧に伴い、血液中や組織中に溶け込んでいた窒素の気泡化が関与して発生し、皮膚のかゆみ、関節痛、神経の麻痺などの症状がみられる。
問17 作業環境管理・作業管理・健康管理
A 粉じん作業を行う場所に設置した局所排気装置のフード付近の気流の風速を測定する。→ 作業環境管理
B アーク溶接作業を行う労働者に防じんマスクなどの保護具を使用させることに
よって、有害物質に対するばく露量を低減する。→ 作業管理
C 鉛健康診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた者を配置転換する。→ 健康管理
D 放射線業務において、管理区域を設定し、必要のある者以外の者を立入禁止とする。→ 作業管理
E 有機溶剤を使用する塗装方法を、有害性の低い水性塗料の塗装に変更する。→ 作業環境管理
問18 局所排気装置
キャノピ型フードは、発生源からの熱による上昇気流を利用して捕捉するも ので、レシーバ式フードに分類される。
問19 労働衛生保護具
防じん機能を有する防毒マスクには、吸収缶のろ過材がある部分に白線が入れてある。
問20 特殊健康診断
特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は、有害物の体内摂取量や有害物による健康影響の程度を把握するための検査である。
関係法令(有害業務以外)7問
問21 衛生委員会
衛生委員会の付議事項には、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することが含まれます。
問22 産業医
産業医の作業場等の巡視の頻度は毎月1回以上であるが、次の情報を産業医が事業者から毎月1回以上受けている場合で、事業者の同意を得ているときは2か月に1回以上でよい。
①衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
②衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
問23 雇入時健康診断
雇入時の健康診断では、医師の判断によって省略できる検診項目はありません。
問24 事業場の建築物、施設等に関する措置
換気設備を設けていない屋内作業場では、開放することのできる窓等の面積を、常時、床面積の20分の1以上としなければなりません。
問25 ストレスチェック
-労働者に対して行うストレスチェック事項-
① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因
② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状
③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援
問26 年次有給休暇
比例付与対象者の有給休暇の付与日数は、次の計算式で求めることができます。
通常の労働者の有給休暇日数×比例付与対象者所定労働日数÷5.2日
(計算後、小数点以下は切り捨てる)
本問を、計算式に当てはめると、
14×4÷5.2=10.769‥‥
小数点以下は切り捨てなので、答えは10日。
問27 妊産婦
妊産婦にフレックスタイム制により労働させることについては法的な制限はありません。
労働衛生(有害業務以外)7問
問28 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン
喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定することは、ガイドラインに定められていません。
問29 労働衛生管理統計
生体から得られたある指標が正規分布である場合、そのバラツキの程度は、分散や標準偏差によって表される。
問30 職場における腰痛予防対策指針
満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるようにする。
満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。
問31 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
システム監査の実施者は、必要な能力を有し、監査の対象となる部署に所属していない等、システム監査の実施に当たって公平かつ客観的な立場にある者であれば、企業内部の者、企業外部の者のいずれでも差し支えありません。
問32 メタボリックシンドロームの診断基準
メタボリックシンドローム診断基準で、腹部肥満(内臓脂肪の蓄積)とされるのは、腹囲が男性では85cm以上、女性では90cm以上の場合であり、この基準は、男女とも内臓脂肪面積が100cm²以上に相当する。
問33 食中毒
O-157は、腸管出血性大腸菌の一種で、加熱不足の食肉などから摂取され、潜伏期間は3~5日。
問34 感染症
人間の抵抗力が低下した場合は、通常、多くの人には影響を及ぼさない病原体が病気を発症させることがあり、これを日和見感染という。
労働生理 10問
問35 呼吸
呼吸のリズムをコントロールしているのは、脳幹の延髄にある呼吸中枢。
問36 心臓の働きと血液循環
大動脈を流れる血液 ➡ 酸素が多い動脈血
肺動脈を流れる血液 ➡ 二酸化炭素が多い静脈血
問37 体温調節
暑熱な環境においては、皮膚の血管が拡張して血流量を増やし、発汗量も増やすことで人体からの熱の放散が促進される。また、熱の産生量を減らすため、内臓の血流量は減少し体内の代謝活動は抑制される。
問38 肝臓
肝臓の機能としてビリルビンの分解はありません。
問39 血液
白血球数・血小板数は、正常値に男女による差がないとされています。
問40 栄養素の消化・吸収
蛋白質は、膵臓から分泌される膵液に含まれるトリプシンなどによりアミノ酸に分解され、小腸から吸収ます。
問41 視覚
明るいところから急に暗いところに入ると、初めは見えにくいが徐々に見えやすくなることを暗順応という。
問42 ホルモン
メラトニン - 脳の松果体 - 睡眠と覚醒のリズムの調節に関与。睡眠ホルモン。
問43 代謝
エネルギー代謝率は、動的筋作業の強度を表す指標として有用。精神的作業や静的筋作業には適用できない。
問44 腎臓
血液中の尿素窒素(BUN)の値が高い場合は、腎臓の機能の低下が考えられる。
衛生管理者試験では、過去問の類似問題が多く出題されます。
見たことがない新しい問題も何問かは出題されますが、過去問をしっかりマスターしていれば合格できます。過去5年分(10回分)の過去問を繰り返し学習することをおすすめします。
衛生管理者試験対策講習会のご案内|合同会社ブルームリンクス
試験に出るポイントに的を絞った講義と、実践的な問題練習を行う講習会を、東京とオンラインで開催しています。
>>衛生管理者試験対策講習会 詳しくはこちらへ
企業内講習(ZOOMオンライン・出張講習)の講師を承ります。
>>衛生管理者試験 企業内講習会(全国) 詳しくはこちらへ