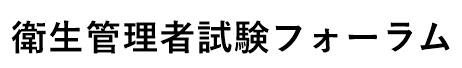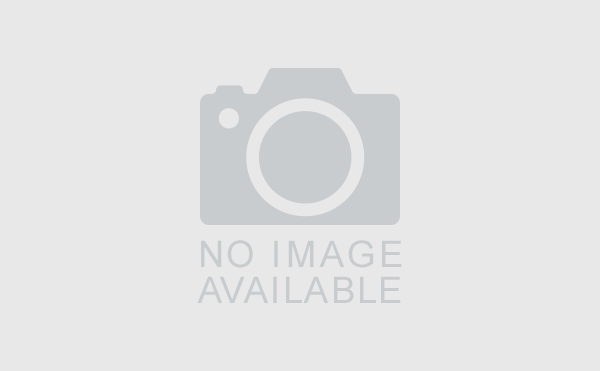第1種衛生管理者試験 平成29年10月公表試験問題(過去問)の出題項目を3分でチェック!
こんにちは。衛生管理者試験対策講習会 専門講師の高山です。
平成29年10月に公表された公表試験問題(過去問)の出題項目を全問整理し、解説コメントを付けました。
◇問題は以下よりダウンロードできます。
第1種衛生管理者試験 平成29年10月 公表試験問題

関係法令(有害業務)10問
問1 安全衛生管理体制
①常時1000人超の事業場
または
②常時500人超で坑内労働又は一定の有害業務(深夜業務は含まない)に常時30人以上従事する事業場
では専任の衛生管理者が必要。
問2 定期自主検査
特定化学設備の定期自主検査の実施頻度は2年以内ごとに1回。
問3 有機溶剤中毒予防規則
地下室の内部の作業場において、常時、第三種有機溶剤等で吹付けによる塗装作業を行うときは、①発散源の密閉、②局所排気装置設置、③プッシュプル型換気装置設置のいずれかが必要です。全体換気装置の設置ではダメです。
問4 作業主任者
作業主任者になるのに免許が必要なのは、
①高圧室内作業主任者
②エックス線作業主任者
③ガンマ線透過写真撮影作業主任者
問5 健康管理手帳
ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した人は健康管理手帳の交付対象になります。
問6 製造許可物質
ベリリウムは、特定化学物質 第一類物質(製造許可物質)
特定化学物質の第一類物質(7つ)を覚えるのはちょっと大変。語呂合わせを作りました。
【衛生管理者試験 語呂合わせ】特定化学物質 第一類物質(7つ)
問7 作業環境測定
放射性業務を行う作業場における作業環境測定は1か月以内ごとに1回。測定項目は空気中の放射性物質の濃度です。
問8 酸素欠乏症等防止規則
空気中の酸素濃度の測定は、その日の作業をはじめる前に行わなければなりません。
問9 粉じん障害防止規則
常時特定粉じん作業を行う屋内作業場における作業環境測定は6か月以内ごとに1回。記録は7年間保存。
問10 労働基準法(年少者の危険有害業務の就業制限)
10kgの重量物を断続的に取り扱う業務は満18歳に満たない人を就かせてもOK。
労働衛生(有害業務)10問
問11 空気中の有害物質
アセトン ➡ 蒸気
問12 リスクアセスメント(化学物質等による疾病のリスクの低減措置の検討)
優先順位が高い方から、
①危険性・有害性のより低い物質への代替
②衛生工学的対策
③管理的対策
④保護具の使用
問13 化学物質による健康障害
塩素による健康障害には、呼吸器障害、肺水腫があります。
☞ 再生不良性貧血はベンゼンによる症状です。
問14 金属による健康障害
鉛 ➡ 貧血、伸筋麻痺、腹部の疝痛
問15 有機溶剤による健康障害
皮膚や粘膜の症状には、皮膚の角化、結膜炎などがあります。
☞ 黒皮症、鼻中隔穿孔は、砒素による症状です。
問16 作業環境における騒音
等価騒音レベルは、時間とともに変動している騒音レベルを一定時間内平均値として表した値。dB(デシベル)で表される。
単位時間(1分間)における音圧レベルを10秒間ごとに平均化した幾何平均値ではありません。
問17 作業環境における有害要因による健康障害
金属熱は、金属の溶融作業などで亜鉛、銅などのヒュームを吸入したときに発生し、発熱などの症状がみられます。
金属熱の『熱』は高温環境の作業とは関係ありません。
問18 作業環境の測定と評価
A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になります。
問19 局所排気装置
キャノピー型フードは、発生源からの熱による上昇気流を利用して捕捉するもので、レシーバー式フードに分類されます。レシーバー式フードにはほかにグラインダー型があります。
問20 労働衛生保護具
防毒マスクの吸収缶の色
一酸化炭素用 ➡ 赤
有機ガス用 ➡ 黒
関係法令(有害業務以外)7問
問21 衛生管理者の職務
衛生管理者の職務に、労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき事業者に対し労働者の健康管理等について必要な勧告をすることはありません。この勧告ができるのは衛生管理者ではなく産業医です。
問22 衛生委員会
議長以外の委員の半数は、事業場の過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき事業者が指名しなければなりません。全委員ではありません。
問23 定期健康診断
定期健康診断で尿検査・血圧検査などは省略できません。
問24 ストレスチェック
ストレスチェックの問題が公開されたのは今回がはじめてです。
解説ブログを書きました。
衛生管理者試験過去問『ストレスチェック』平成29年10月公表問題【 第一種 問24・第二種 問5】
問25 衛生基準
食堂の炊事従業員については、専用の便所と専用の休憩室を設けなければなりません。
問26 年次有給休暇
労使協定により、時間単位で有給休暇を与える対象労働者の範囲、日数(5日以内に限る)等を定めた場合において、対象労働者が請求したときは、有給休暇日数のうち当該協定で定める日数について時間単位で与えることができる。
問27 妊産婦
妊産婦が請求した場合には、管理監督者も含め深夜業をさせることはできません。
労働衛生(有害業務以外)7問
問28 厚生労働省『事業場における労働者の健康保持増進のための指針』
《削除》
問29 厚生労働省『労働者の心の健康の保持増進のための指針』
メンタルヘルスケアでは、次の4つのケアを継続的かつ計画的に行うことが重要。
◆4つのケア
➀セルフケア
②ラインによるケア
③事業場内産業保健スタッフ等によるケア
④事業場外資源によるケア
☞4つのケアに同僚によるケアはありません。
問30 厚生労働省『VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン(※)』
VDT作業では、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10~15分間の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けるようにする。
※令和元年7月より『情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン』に変更されました。
問31 出血及び止血法
静脈性出血 ➡ 傷口からゆっくり持続的に湧き出るような出血。
動脈性出血 ➡ 拍動性で鮮紅色を呈し、出血量が多く、短時間でショックに陥る出血。
問32 骨折
単純骨折 ➡ 皮膚の下で骨が折れているが、皮膚にまで損傷が及んでいないもの。完全骨折と不完全骨折の場合があります。
複雑骨折 ➡ 皮膚や皮下組織の損傷を伴うもので、骨折端が皮膚を破って外に出ている場合もある。開放骨折ともいいます。
問33 食中毒
腸炎ビブリオ ➡ 感染型食中毒
問34 虚血性心疾患
運動負荷心電図検査は、虚血性心疾患の発見にも有用です。
労働生理 10問
問35 血液
血漿中の蛋白質のうち、アルブミンは血液の浸透圧の維持に関与している。
問36 心臓の働きと血液の循環
心筋は不随意筋で横紋筋。
問37 肝臓
肝臓の機能に乳酸の合成はありません。
問38 呼吸
呼吸中枢がその興奮性を維持するためには、常に一定量以上の二酸化炭素が血液中に含まれていることが必要。
問39 体温調節
発汗のほかに皮膚及び呼気から水分が失われる現象を不感蒸泄といいます。
問40 腎臓・尿
腎臓は、背骨の両側に左右一対あり、それぞれの腎臓から1本ずつの尿管が出て膀胱につながっている。
問41 神経系
交感神経系 ➡ 心拍数を増加し、消化管の運動を抑制させる。
副交感神経系 ➡ 心拍数を減少し、消化管の運動を亢進させる。
解説ブログを書きました。
衛生管理者試験過去問『神経系』平成29年10月公表問題【 第一種 問41・第二種 問27】
問42 感覚又は感覚器
眼は、水晶体の厚さを変えることにより焦点距離を調節して網膜上に像を結ぶようにしている。
問43 ストレス
典型的なストレス反応として、副腎皮質ホルモンの分泌の著しい増加がある。
問44 ホルモン
ホルモン名・内分泌器官・はたらきの組み合わせを選ぶ問題はよく出題されます。
メラトニン - 脳の松果体 - 入眠・睡眠維持作用
衛生管理者試験では、同じような問題が繰り返し出題されますので、過去問を中心に学習することが重要です。
本試験では見たことがない新しい問題も何問かは出題されますが、過去問をしっかりマスターしていれば、合格する可能性は高いです。過去5年分(10回分)の過去問を繰り返し学習することをおすすめします。
>>衛生管理者試験フォーラム TOP
講習会を東京とオンラインで開催しています。
>>衛生管理者試験対策講習会 詳細
企業内講習(出張講習・オンライン講習)の講師を承ります。
>>衛生管理者試験 企業内講習会(全国) 詳細